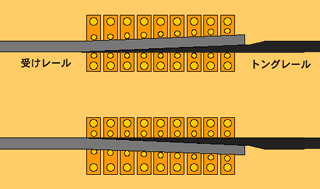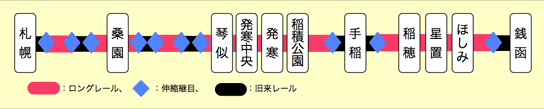延びても大丈夫 ロングレールと伸縮継目 〜JR琴似駅〜
JR琴似駅ホームで電車を待っていると、電車が静かにホームへ入ってきます。琴似駅構内のレールには隙間の空いている継目がないので「ガタンゴトン」と音がしません。このレールは通常のレールより長く、「ロングレール」と呼ばれています。ホームの端から端まで歩いて線路を見ても、継目が見あたりません。それでは次にホームの札幌側の端に立って、小樽方面行き線路の数メートル先をよく見てください。変わった形をしたレールの継目が見えます。これはロングレールの端に設置される「伸縮継目」です。鉄は暖まると伸び、冷えると縮みます。その伸び縮みによりレールがゆがまないようにするための仕組みです。今回はロングレールと伸縮継目について紹介します。
- 写真:琴似駅の札幌側の伸縮継目を望む。 伸縮継目のアップ。
【旧来のレール】
まずは旧来のレールについて紹介しましょう。これは札幌駅構内でも見ることができます。一本のレールの長さは通常25mです。決まった長さのレールなので「定尺レール」と呼ばれます。それらを「継目板」とボルトで接続しています。一般的に継目には1cm程度の隙間が空いています。これは、鉄などの物質は暖まると膨張し、冷えると収縮する性質を考慮したものです。
- 写真:旧来レールの隙間がある継目。
この隙間があることで、夏にレールが暖まって延びても、隣のレールとぶつかり合うことがなく、レールがゆがみません。しかし、猛暑などにより想定以上に暑くなると、この隙間では解消できないほどにレールが延びてしまい、レールがゆがんで、電車の運行に支障をきたすこともあります。一方冬には、冷えることによってレールが縮むので、隙間は大きくなります。その隙間を電車の車輪が通過することによって「ガタンゴトン」と音がします。振動も大きく、電車の乗り心地は悪くなります。そのため旧来レールの欠点を克服した「ロングレール」が普及してきたのです。
【 ロングレール】
琴似駅札幌側の伸縮継目から手稲駅札幌側の伸縮継目までの約6.4kmはなんと1本の長いレールです*1。ロングレールを使用することにより、騒音が小さくなり、振動が小さくなることで乗り心地も良くなります。
床面と枕木で固定されている長いレールは、中央部分がしっかり押さえ込まれているので、あまり動かない不動区間があることが研究によりわかってきました。温度変化により伸縮する可動区間は両端それぞれの100m程度です。そこで、何本ものレールを溶接でつなぎ合わせ、不動区間が存在する長さ200m以上のレールを「ロングレール」と呼びます。
温度変化による両端それぞれの伸縮量は5cm程度にものぼります。そのため旧来の隙間がある継目では対応できません。そこで両端に「伸縮継目」という特殊な継目を設置する必要があります。
【 伸縮継目】
伸縮継目は、特殊な形状をした「トングレール」と「受けレール」が組み合わされています*2。トングレールは先端が細くなっていて、受けレールはその外側にあります。トングレールと受けレールは伸び縮みしても接しながらずれるだけなので*3、継目には隙間が空きません。そのため車輪は滑らかに通過することができます。
- 図:伸縮継目の模式図
JR北海道で最も長いロングレール区間は、長さ53kmの青函トンネル内にあります。温度変化が小さいトンネル内なので、とても長いロングレールが実現できました。
札幌近郊もロングレールがだんだんに普及してきました。
線路がロングレール化されることにより、電車の速度は向上し、騒音は小さくなり、乗り心地が良くなります。みなさんも電車に乗った時に、車輪とレールとの音に注意を払ってみてください。「ガタンゴトン」と音がしない区間がわかるでしょう。
でも私は、あの「ガタンゴトン」という音に懐かしさを感じるので、それが聞かれなくなるのは少し寂しい気がします。これからの子どもが「電車ごっこ」をするときには、どんな音を唱えて遊ぶのでしょうか?
JR琴似駅
- 【アクセス】:JR札幌駅から電車で5分
【参考資料】
- 徹底図解鉄道のしくみ、新星出版編集部、新星出版社
- 鉄道用語事典、久保田博、グランプリ出版
- 鉄道工学ハンドブック、久保田博、グランプリ出版
(文・写真・図 大鐘卓哉)
この記事を読んで面白いと思った方、クリックしてくださいね。
*1:ロングレール区間でも、信号のところでは継目板とボルトでレール同士をつないでいる。これは信号用の電気が流れないように絶縁物質をはさんで隙間なくつなぐ「絶縁継目」である
*2:一般にトングレールのとがった方が電車の進行方向に対応するが、必ずしもそうではない。電車が双方向で走る単線区間にもロングレールと伸縮継目が設置されている。
*3:ロングレールの端が受けレールの場合、トングレールに沿って受けレールが伸び縮みする。一方、ロングレールの端がトングレールの場合、トングレールが伸び縮みすると受けレールが広がったり狭まったりする。
*4:線路の切替ポイントはロングレール化できないので、ポイントの前後に伸縮継目が設置されているようだ。